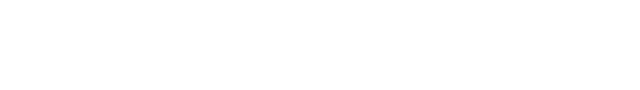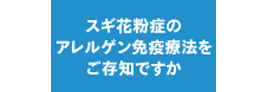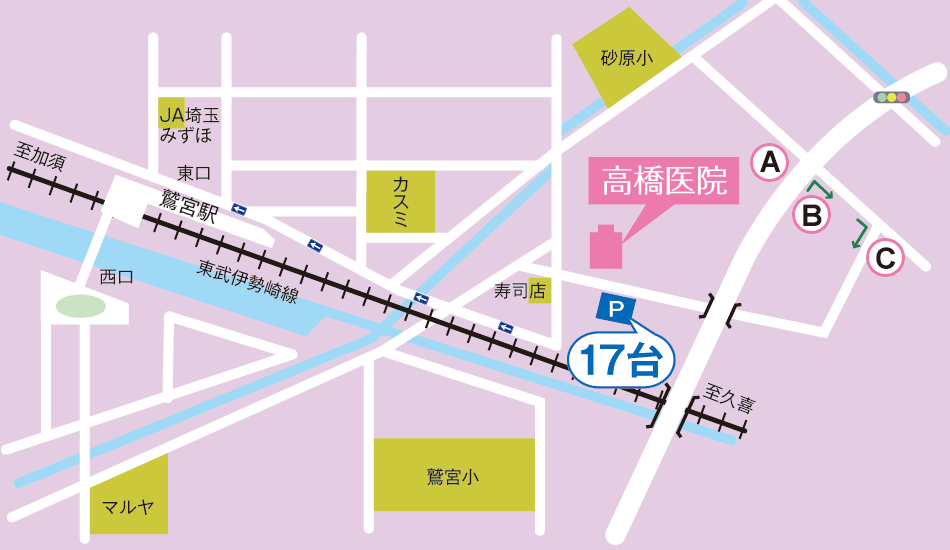冷え症
冷え症
急に気温が下がり、手足や体全体の冷えを感じる方も多い季節になりました。特に今年は、秋がなく、夏から真冬の気温になったため体が気温の変化についていけない方もかなり多いと思います。冷えは免疫力を低下させ、感染症、頭痛、だるさなどの原因になります。
男性よりも女性のほうが5倍ほど多い冷え症にはタイプごとの治療方法があるのでここでご紹介します。
このような症状ありませんか?
- 手足が冷たい、温めてもなかなか温まらない
- あかぎれ・しびれ・しもやけ
- 関節痛・腰痛・頭痛・肩こり
- 身体が冷たい
- 膀胱炎・頻尿
- 顔色がくすんでいる、目の下にクマができやすい、肌が荒れやすい
- 疲れやすい、倦怠感を感じる
- 風邪をひきやすい
- 食欲不振、胃もたれ、お腹の張りを感じる
冷え症の原因
多くの場合、寒さで血管が収縮することにより手足の血流が低下することが原因ですが、下記の1つでも冷えの原因になります。
筋力の低下
運動不足が続いてしまうと筋肉が劣れてしまい、血行が悪化します。とくにふくらはぎは血液を心臓に戻すためのポンプとして機能しています。ふくらはぎの筋肉が落ちてしまうとポンプ機能も衰えてしまうので、きちんと運動する習慣を作りましょう。
基礎代謝の低下
生命活動を行うのに欠かせない、必要最低限のエネルギーを「基礎代謝」といいます。基礎代謝が低くなると体温が低くなり、冷え症が起きやすくなります。
食生活の乱れ
栄養バランスが偏った食習慣が続いてしまうことでミネラルやビタミン不足になりやすく、血の巡りが悪くなります。
ストレス
緊張すると血行不良が起きやすいため、そこから冷え症になりやすいです。
自律神経の乱れ
身体の体温をコントロールしているのは自律神経です。近年はエアコンなどの影響で季節関係なく、快適に室内で過ごせるようになった結果、気温に対する感覚が鈍くなり、自律神経が乱れやすくなりました。
また、腸の運動も自律神経によって左右されるものです。そのため自律神経が乱れると下痢・便秘も起きやすくなり、基礎代謝も低下してしまい、冷え症へ繋がってしまいます。
喫煙
喫煙習慣があると血管が急に収縮することが多くなるので、冷え症が起きやすくなります。
冷え症の4タイプ
冷えにはさまざまな原因が絡んでいます。そのため冷え症のタイプによって、対策方法がそれぞれ異なります。あなたはどのタイプに当てはまりますか?
手足が冷えるタイプ ―四肢末端型―
食事の量が少なかったり、過度なダイエット、偏った食事による栄養不足、運動不足などの生活習慣によって交感神経が過剰に働き、手足の血管が収縮するため手足がとても冷えます。若い女性に多い冷え症で、肩こりや頭痛も合併することが多いタイプです。
体を温める食べ物や飲み物を摂取したり、カイロでお腹や腰などの保温を心がけましょう。
食事の量が少ない、運動不足などの生活習慣によって交感神経が過剰に働き、
下半身全体が冷えるタイプ -下半身型-
長時間のデスクワークによりお尻やふくらはぎの筋肉のコリによる下半身の血行不良による冷え症です。加齢とともに起こりやすくなります。ストレッチ、スクワット、ふくらはぎのマッサージ、足首回しなどの運動と入浴・下半身浴が有効です。
内臓が冷えるタイプ -内臓型-
交感神経の働きが弱いことが原因で手足の血管が収縮できなくなり、手足は温かいが、下腹部や二の腕に冷えを感じたりするタイプです。ストレスが原因で起きやすい冷え症で手足の冷えを自覚しないため、下痢や倦怠感、免疫低下により風邪をひきやすい状態です。体を温める食べ物や飲み物を摂取することで、内臓の冷えを予防しましょう。
全体が冷えるタイプ -全身型-
ストレスや生活習慣の悪化によって、基礎代謝の低下が原因で、身体全体が冷えてしまうタイプです。倦怠感や免疫低下により風邪をひきやすく、下痢ぎみ状態です。ただし、甲状腺の病気などが潜んでいる可能性もあるので採血などの検査が必要な場合があります。
心がけたい温活
なにをおいても体を冷やさないことが一番大切です。
一、二に防寒が大切です。一度、冷えると冷え症の方はなかなか温まりません。そこで、帽子、厚手のマフラー、手袋、靴下もできればカシミヤやヤクなどの少し値段の高めの厚い靴下をお勧めします。また、手軽な方法として、貼れる使い捨てカイロで背中、腰を温めると全身がとてもホッコリします。
1日のはじまりに「コップ一杯のぬるめのお湯」
交感神経が刺激されるので、基礎代謝アップや目覚めの良さにも効果的です。
「エスカレーター」から「階段」へ
全身の筋肉の運動により、代謝がよくなり、体温が上がります。
座り作業が多い時は「ひざ掛けを」お供に
長時間座りっぱなしで仕事をし続けると下肢を含めた全身の血流が悪くなります。1時間に1回は体を動かして血行を少しでもよくすることとひざ掛けを忘れないように。
お食事のときは「身体を温める食材」を心掛けて
温かい食べ物と温かな飲み物を。また、食材としては玉ねぎ、かぼちゃ、いんげん、生姜やネギ、ニンニク、ごぼうなどの根菜類(寒い土地でとれる野菜は体を温めます)。
時々、深呼吸で心身を整える
デスクワークなどの作業中は呼吸が浅くなっているめ、酸素が十分に体に取り込まれず、筋肉もこわばって血流も悪くなってます。「深呼吸」を時々して、酸素をたくさん体内に入れることで、身体の細胞が活性化するとともに全身の血行もよくなります。また、リラックス効果によりストレスによる緊張をほぐしてくれます。
お食事や飲み会の際には
お酒は体を冷やす飲み物のため、冷え症の方にはお勧めできません。「赤ワイン」など少しずつ飲みましょう。
寝る前にはストレッチを
軽いストレッチを行うだけで体は少し温まります。それでも足が冷える方は足首の締め付けない靴下をはきましょう。また、温かい飲み物を飲むようにしましょう。
冷え症の基本治療
まずは身体全体を温めて全身の血行を改善させます。
入浴・半身浴
冷えを予防・改善するためには、きちんと湯につかることが大切です。38〜40℃くらいのぬるめの湯にゆっくりつかることで、副交感神経が優位になり、手足などの末梢の血管が拡張することで全身の血流がよくなります。また、水圧によって足腰などの筋肉の緊張が緩み、血流が良くなって手足まで血液が行き渡るので、冷えやむくみの改善に効果があります。
お湯につかる時間は、10分間くらいを目安にします。連続して湯につかっている必要はありません。何回かに分けて合計10分間、湯につかるとよいでしょう。
できれば毎日、ぬるめのお湯に汗ばむくらいまで温まってください。また、入浴後は冷えはじめる前に靴下を履いてください。
運動
運動することにより血行が良くなり、全身に酸素と栄養素が行きわたって新陳代謝が促進し、体温も高くなって基礎代謝もアップします。
ハードな運動は特に必要ではなく、エスカレーターを階段にしたり、歩くだけでも毎日行えば効果が現れます。
ストレッチ
ストレッチはこわばった筋肉をほぐして血行を改善させるので、仕事中や就寝前に軽いストレッチにより血行が良くなり体温も上がるため、ぐっすりと眠ることができます。
股関節や足首を左右回転などで股関節、足首、足の血行をよくるす方法があります。
1日30回ぐらいはクルクル回しましょう。
特にアキレス腱やふくらはぎの筋肉を伸ばすストレッチも第二の心臓といわれている下腿三頭筋を柔らかくすることによって全身がホカホカします。
内服治療
ビタミン剤や漢方薬が処方される場合もあります。薬以外の治療法は、基本的に食事、生活習慣の見直しや運動不足の解消などです。
「ビタミンE(トコフェロール酢酸エステル)」の内服で、手足の血管を拡張することにより体の隅々まで血液の流れをサポートする効果が期待できます。通常の300mg/日で効果の出ない場合、増量が必要になります。
また、漢方薬ではタイプ別に処方されます。
手足が冷える人向け
当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)
血行を促して体を温め、手足など末梢を温める働きがあります。冷えによる頭痛や下腹部の痛みをやわらげる効果も期待でき、しもやけなどにも使われます。成分の1つの生姜に「ビタミンE」をプラスするとかなり改善効果が期待できます。
おなかが冷える人向け 大建中湯
疲労・倦怠感、貧血、食欲不振、寝汗などを伴う冷え性向け十全大補湯
ツボ(圧迫する お灸 針)治療
ツボは、10〜15秒かけてゆっくり軽く押して、両側1〜2分間ほど繰り返します。
痛みが強い場合は、気血が滞っている証拠です。
押す力は、「気持ちいい」くらいの強さで十分効果が出ます。↓
合谷(ごうこく)
手の甲を上に向けて、親指と人差し指の骨が合わさるところです。
一番手軽に押せるツボです。
血流を改善するツボですので、冷え性に効果的です。
三陰交(さんいんこう)
足の内側のくるぶしから指4本分上がった所です。
生理不順、更年期症状、むくみなど女性特有の症状にも効果的です。
太渓(たいけい)
足首の内くるぶしとアキレス腱との間にあるくぼみです。
全身の血をめぐらせる働きがあり、血液循環が良くなり、冷えが改善します。
太渓(たいけい)を押して得られる効果は以下のとおりです。
・アンチエイジング・頻尿予防・改善・冷え性改善・生理痛の緩和・妊活
湧泉(ゆうせん)
足裏で母指の内側の凹んだ所です。
下半身の冷え症やむくみ、疲労回復に効果があります。
久喜市上内1746 高橋医院(鷲宮)
内科(高血圧 胸痛 動悸 脂質異常症 糖尿病 睡眠時無呼吸症候群(CPAP治療) 不眠症 呼吸器 消化器 便秘 認知症 物忘れ 肥満症 ダイエット) 循環器内科 健康診断 皮膚科 美容皮膚科 巻き爪 アトピー性皮膚炎
TEL 0480-58-87